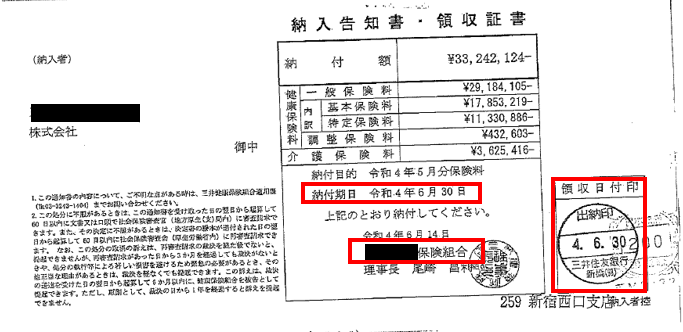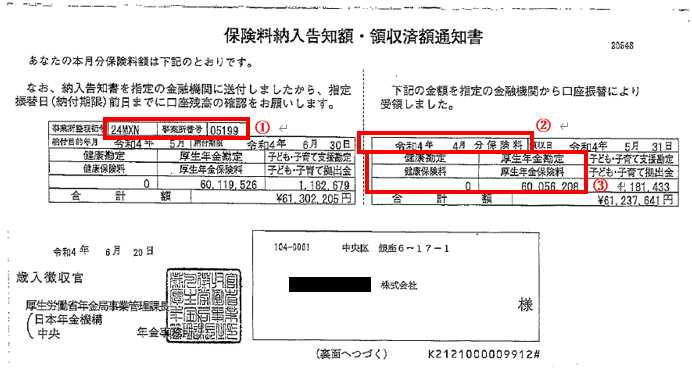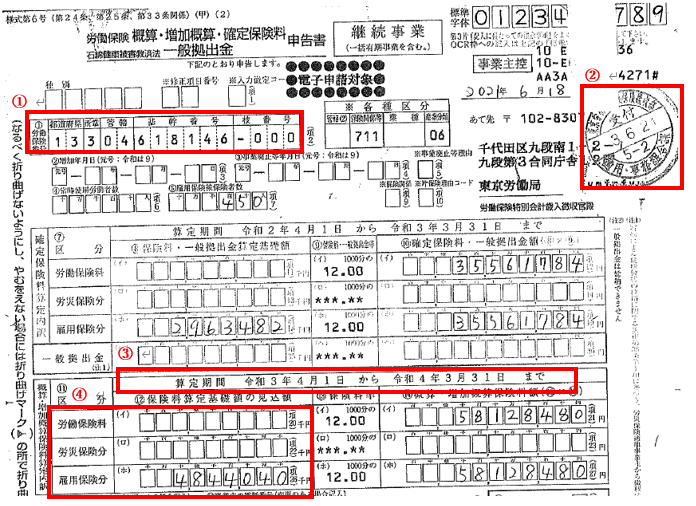【質問】
宅建事務所について、従業者名簿に載る事務所はあくまで常勤(常駐)する事務所として間違いはないでしょうか。
弊社の場合、例を挙げますと東京コンサルティング営業部に所属しているが、勤務場所は東京西支店の事務所である担当がいるとします。
東京コンサルは東京事業本部の宅建事務所に含む分類をしており、あくまで事務所は新宿となっています。
よってこの担当は、所属は東京コンサルであるが東京事業本部の事務所の常勤性はなく、東京西支店の常勤性があることになります。
この担当は東京事業本部でも東京西支店でも専任取引士にはなりませんが、従業者として名簿上はどちらの事務所に入れるべきものなのでしょうか。
常勤性でしたら東京西支店の名簿ですが、
この担当は所属が東京コンサルなので、東京コンサル部長の契約をすることになる場合があるが、契約名義の従業者名簿に載っていなくとも(そもそも東京コンサルの事務所登録はなく東京事業本部ですが)問題はないのでしょうか。
※名刺は東京コンサルですが、持っている従業者証明書の所属事務所は東京西支店である勤務地は同じであるため
※政令使用人(事務所の代表者)が管理できる対象は、やはり常勤している者になるはずです出先の宅建事務所はそもそも契約名義(支店長・部長)ではない代表者(所長)であったりしますので、あくまでも常勤というところで判断していいでしょうか。
専任取引士の定義は
「当該事務所に常勤」する「常勤性」と「専ら宅建業に従事」する「専従性」の2 つであると思いますが、専任取引士以外の従業者はどのように名簿に振り分けるべきなのでしょうか。
【SGの回答】
ご質問の件について、関東地方整備局のクサズミ氏に照会したところ、ご認識の通り、やはり常勤性での判断となるとのことでした。
(あくまで実態ベースでの判断となります)
所属は東京コンサルティング営業部ですが実際は東京西支店に勤務している場合は、従業者名簿は東京西支店となります。