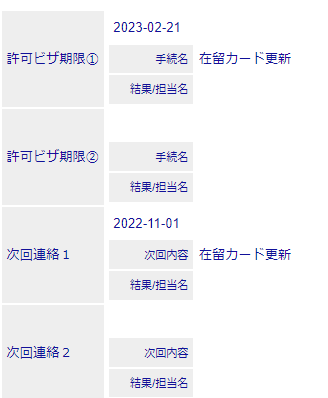※ 入札・一括・大量案件の完了決裁はこちら
目的
・問題点や課題を洗い出して、検討する
・展開:紹介等により、業務が続いていくようにする
完了決裁の提出期限
①完了MTG提出(決裁:案件決裁者)
→翌月1営業中
②COMPの入力違い・キャンセル・不許可決裁
→翌月1営業日午前中
③経企デキスギ入力
→〆毎(期限は別途リリース)
④経企非定例業務
→翌月1営業日中
※決裁について
①②は翌月2営業日中まで、③は翌月2営業日午前中まで、④は翌月1営業日中
※業務完了後、1週間程度を経っても、完了MTGが終わっていない案件は、管理担当とSPの完了業績を0とすることがあります。
管理担当は、すぐに終えるようにしましょう。
案件完了時の流れ
・完了MTGでは、案件の進行全体を振り返り、良かった点・
完了MTGは、展開(リピート・紹介)を検討して実行する場でもあります。完了MTGのメールには、展開案を入れるようにしてください。
方針MTGと同じ要領で、案件決裁者から決裁を受け、
・完了決裁依頼時、COMPの案件ページに証左のデータをアップロード。
・証左は、直接的な証左として必要最低限の許可証や届出書受領印付控等。
・入札、コンサル業務等の直接的な証左が難しい場合、完了決裁者に例外対応を決裁依頼。その場合、業務完了を判断できる文書や画像等で代用(顧客からの業務完了確認メールスクショ等)。
・完了決裁者は、完了決裁時に当該証左を確認。
【アンケート依頼】
①業務完了時に、管理担当者(又は受任担当者)から顧客に直接アンケート案内する
※年間・顧問・一括案件は、契約更新時
※領収書案内メールにも、引き続きアンケート貼付します
②完了決裁時に、決裁者は、アンケート直接案内履歴を確認する
(アンケート依頼も、完了決裁の条件とする)
③管理担当者は、アンケート回収率8割以上を目安にする
※按分は「按分シート」を参照すること。
※完了決裁者からFBがあった場合は必ずインラインで返信すること
「完了決裁済」で決裁完了となるので、それまではやり取りを続けること
補足事項ー完了決裁について
【目的】
①展開すること
②案件の振返りと対策
③適切な按分の確認
【チェック項目】
・適切に按分できているか
・基本按分割合と異なる場合は按分備考に記載があるか
・サポート期限が入力できているか
・完了日が入力できているか
・ステータスを変更しているか
・完了MTGを記載しているか
・完了決裁メールを送る際、案件URLを載せているか
・完了決裁済のメールがあり、日報にも「完了決裁済」と決裁者が入力しているか
・該当する案件の場合、以下について入力できているか(2022.11更新)
【許可ビザ期限①】/手続き名
【次回連絡1】/次回内容
例: