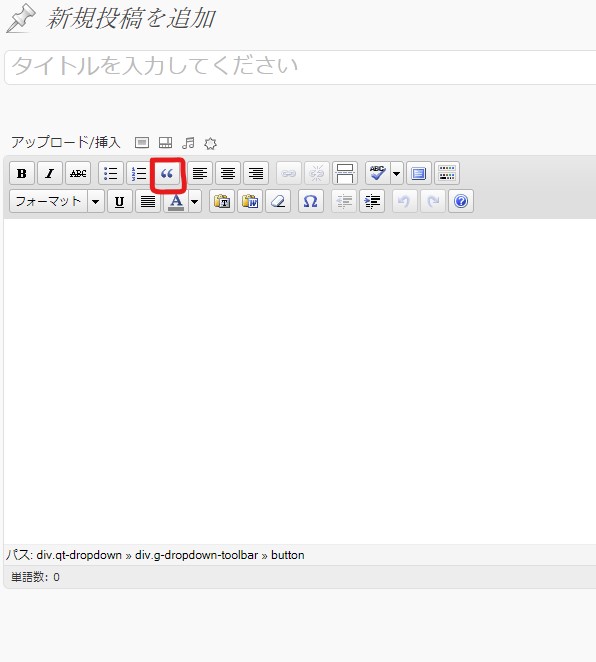【1. 完了とは】
原則、許可が出て、完了MTGを行い決裁をもらったら完了となります。
終了日は完了MTGを送付した日です。
長期大量案件は、翌月2営業日以内に送ったとしても当月最終日の日にちを記載してください。
なお、大量案件は、月末に受任/完了が同時に計上されますが、エコ・事業認定など一部の大量案件は月初9営業日時に、中間でその時点での受任業績を計上します。
なお書類納品は納品時後に、完了MTGを行った後が完了になります。
【2. 按分確定の流れ】
① 受任時に受任担当が着手時按分を決定
② 管理担当がCOMP関係社員欄に入力
③ 案件完了時の完了MTGにて合議の上、
受任担当が最終按分を確定・決裁。
管理担当でやるべき対応を受任担当が行った場合は、貢献度に合わせて、SPとして受任担当に計上。
【3. 基本按分比率】
一つの案件には以下のような役割があり、貢献度に応じて報酬額から案分された業績が、関わったメンバーにつきます。
○開発 5~10% その案件を柱にした人への按分
○展開 5~10% その案件を展開させた人への按分
○受任 ~30% その案件の受任の受任担当者(1人のみ)
○管理 30~55%程度 その案件の管理担当者(1人のみ)
○SP 5~30%程度 管理担当をサポートしたスタッフの按分
○在宅 原則20% 在宅活用の按分
○決裁 5~20% 行政書士決裁者の按分
○提出 5% 入管手続きがある場合の按分
PP/AP/NI/アルバイト等社内にいるメンバーは全員按分の対象となります。
* 受任/管理/決裁は全ての案件に入力してください。重複記載はNGです。また順番も遵守してください。
* SPはWチェック、受任担当による管理フォローなどがあたります。
割合は完了MTG時に業務時間ではなく、業務量に即して確定させてください。
* 決裁担当が取次を行う場合は分けて記載しないでください。
* 取次について
取次:5%(決裁から控除して按分すること)
(申請者が取り次ぐ場合は、決裁を10%とする)
* 語学力を使っていたり、専門知識があってアポにつなげた場合はSPに含みます。
【4. 展開担当について】
【展開】 → 展開のルールはこちら
【5.在宅の按分ルール】
在宅スタッフ依頼分を、【報酬内経費】に含める運用にします。

【内訳】に記載する内容
・在宅への依頼分 コマ単価×依頼時間 例)山田2000 ※在宅さんの名前を入力する
・経費内容 例)交通費5000 ※宿泊の有無に関わらず入力(特急料金・タクシー代など)
外注費20000
・支払手数料の紹介元 例)60232 片山商会
在宅スタッフの1コマ単価は在宅スタッフ一覧にて確認してください。
コマ数に関わらず、在宅依頼をした場合は記載と計上が必要です。
※報酬内経費欄に、内訳の合計金額を入れるのを忘れないように。※
<方針MTG時>
今後、作成する案件は見本の通りに作成してください。
※【報酬内経費】は受任時で確定している経費はいれること
<完了MTG時>
新しい運用に合わせて、入力を変更してから完了MTGを受けてください。
★【支払紹介料】がパーセントで入っている場合は必ず金額に変更すること
【6. 管理担当は1人】
大量/一括含め、どの案件も基本的に管理担当は1人とします。
実質的に2人が管理をしているという場合にも、Compの管理担当欄(関係社員欄ではなく)に
記載しているスタッフを管理担当とし、もう一人のスタッフはSPとしてください。
【7. 受任担当も原則(通訳対応など受任担当7は複数可)】
原則受任担当も一人です。
ただし通訳を行ったスタッフがいる場合など、
受任に多大な影響を与えたスタッフが受任担当の他にいる場合
例外的に受任担当を二人設定することが可能です。
なおCompの旧来からある受任担当欄には、メインの受任担当のみ記載してください。
管理担当にリピートの連絡があった場合、受任は元の受任担当になります。
ただし、管理担当が他社を紹介してもらった場合は、受任を管理担当が行うことができます。
【8. 退職者の対応】
進行中の案件で受任担当が退職した場合は、案件完了時に退職者に按分してください。
進行中の案件で管理担当が退職した場合は、
管理担当を引継し、変更して、退職者をSPとして、その時点での
申請中の案件で管理担当が退職した場合は、管理担当を引き継ぎ、
原則引継者を管理担当として5%按分してください。
(申請後が非常に重い案件の場合は、業務量を勘案して増やしてください)
(なお2019年8月以前に、申請中案件を退職者から引き継いだ場合は、完了業績に計上しません。)
リピート/紹介案件で紹介元案件の対応者が
退職している場合は、開発/展開担当リストのスタッフを担当にしてください。
【帰化について】
①退職者が管理担当として申請した案件を引き継いだ場合
帰化は審査期間が長いこともあり、申請後も一定の割合で顧客対応をした案件もあると思います。
上記案件につき、完了業績をつけることができるようになりました。
この場合、引き継ぎ案件ということも含め、個別に按分・完了MTGの決裁を行ってください。
②完了を確認出来ない場合について変更
申請受付から1年半程度経っても官報でも見つけられない、顧客とも連絡がとれない等、
案件決裁者に完了見込みとして決裁をあげて完了することができます。
上記、年に2件以上あった場合は、鈴木さん宛に報告書を提出することになりました。